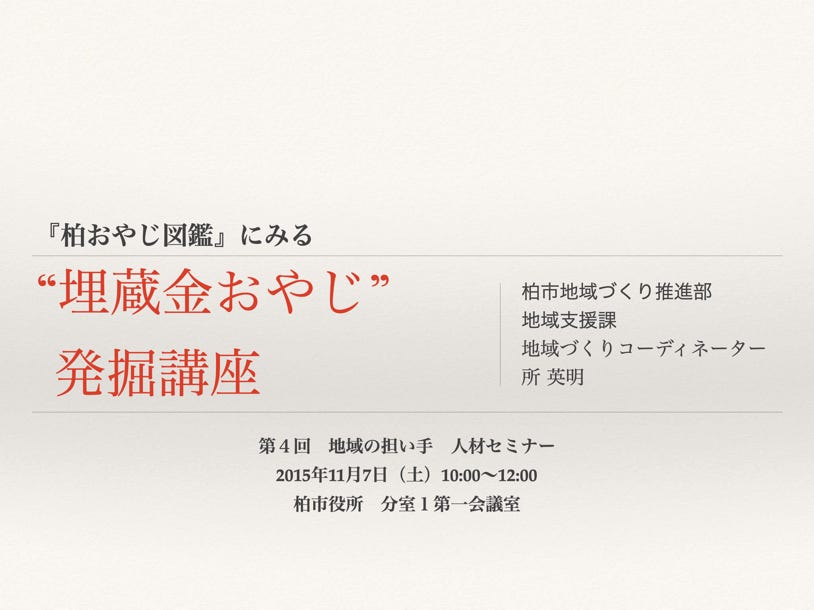26/02/2021
この「エッセイ」カテゴリでは、リアルタイムで雑文を書くこともあるけれど、昔書いた文章をいわば地層から「掘り出して」載せたりもしたいと思っています。そういう意味でも、本当に個人ホームページで、ぼく以外の人が読んでも、なんのこっちゃ。ということになりかねない。
なりかねないんだけれど、実はそれなりに面白い。と思ってもらえるようにしたい、とは思っているんですが。
どうかな?
今回は、Macのフォルダを開いたら見つかった、こんな文章。
最近は開かれなくなってしまったけれど、小学校の同窓会での、閉会の挨拶の下書きです。
誰でもそうなのかもしれないけれど、子供から大人になって、忙しい社会人が一段落した頃、同窓生に会いたくなって、ん十年ぶりに同窓会をやりました、というのはよくある話です。
やってみて、よかったのか、いや、がっかりだよ、ということになるのか、はともかくとして。
みなさんは、どうでしょうか。
✳︎ ✳︎ ✳︎
閉会の挨拶
えー、栗林君が閉会の挨拶をやれ、ということでわざわざ訪ねてきてくれて依頼されましたので、少々喋ります。確かお前のために60分ほど時間を取ってあるということで‥‥いや、60秒? もしかすると6秒だったかもしれませんが、もう過ぎましたね? では6分ほど喋らせて頂こうかと思います。
栗林君がうちに来たのは、単に携帯電話が繋がらなかったので、直接来ただけなんですが、挨拶を引き受けたあとで、丁度読んでいた小説のことを思い出しました。ティム・オブライエンという作家の「世界のすべての七月」という本で、村上春樹が訳しています。オブライエンも村上さんとほぼ同世代で、だから、我々より一回り近く上の世代になります。
その「世界のすべての七月」が、言ってみれば同窓会小説とでも言うようなものなんです。作者のオブライエンは村上さんと同世代なのですが、この物語の中では書かれた時期のせいで丁度今の我々50とか51歳とかの同世代として出てくる。
誰が主人公という書き方ではなくて、一人ひとりの同窓生たちを主人公にした短編小説を積み重ねるようにして長編を作っています。後半に行くに従ってその同窓生たちが相互に絡み合ってくる、という一種の群像劇で、ある者は未だ独身でじたばたしているし、ある者は離婚の傷を引きずっている。ある者は婚約者の裏切りを今でも許せずにいる。ある者はちょっとした瞬間にベトナム戦争の戦場にフラッシュバックして心理的トラウマに飲み込まれてしまう。一見非の打ち所のない結婚生活を送っていて成功者と思われている女性がガンで乳房を失っていて夫から女として見られなくなってしまったと深く悩んでいる。ある者は天職と思っていた仕事を失ったばかりだし、ある者は犯罪に巻き込まれて既に死んでいます。
小説ですから誇張して描いている部分はもちろんあるわけですが、読んでいるうちに、ちょっと離れて冷静に見れば、とんでもないそのドタバタが、切なくも愛おしく、我々自身の似姿として見えてくるようなところがあるわけです。
もちろん、その小説の主人公たちと僕たちは違うと言えば全然違うわけで、日米の違いがそもそも大きいですし、その小説では大学の同窓会なんですが、我々のは小学校というわけで、大学と小学校では自ずといろいろ違っていて当然でもあります。
そうですよね? 大学時代を一緒に過ごす、というのと小学校を同級生として過ごすというのはかなり異なる体験ですよね。
我々は、言わばようやく人間になりかかったところで出会った。我々一人ひとりの原型は間違いなくそこにあったけれど、まだ今現在の我々にはなっていなかった。つぼみだったわけです。ぼくも、あなたも。
その後、立派に大輪の花を開花させたひとも、僕みたいにしょぼしょぼっとろくに花も咲かせずに現在に至っているひともいるでしょうが、いずれ小学生のころの僕もあなたも、気が付くと半世紀を生きてきた。その間にはかなりギャップがある。
北村薫さんという小説家が「スキップ」というとんでもない設定の小説を書いています。昭和40年代の初め、17歳だった女子高生がある日レコードを聴いていて眠ってしまった。そして、目覚めたら夫と17歳の娘がいる42歳のお母さんになっていたんです。その間の記憶が全くない。別に時間を跳躍した、とかそういう話ではないんです。確かに生きて歳を取った。ただ、その間の記憶が欠落しているんですね。すると、本人の主観では、いきなり17歳のある日から、42歳にジャンプしてしまったようなことになる。もうえらいことです。
言ってみれば、今日の我々はそれに近い。自分が、というより、相手が、ですけれど、いきなり50歳にジャンプしてしまった。間がすっぽりと抜けている。
小説の方では、主観的には17歳の、しかし実際には42歳の主人公は、もちろんすごく混乱するのですが、それでも何とかそれを受け止めて、わたしをもう一度わたしとして生きていこう、と健気に歩き始めるんです。
ですから、我々もそれに倣って、なんとか一緒に生きていこう、と考えていいのじゃないかと思います。本当のところ、一瞬自分のことはさておいて、このおじさんは誰だ? とか、このおばさんがあの可憐だった○○子ちゃんであるなんて信じられるか、とか思うわけですが、まぁ、スキップの主人公に比べれば、まだまだ甘い。なんとかなる。というより、ぼくはいっそ、お互いにほとんど初めまして、と言った方がいいようなものだ、と思うんですね。
実際、同窓生とはいいつつ我々は互いによく知らないでしょう、多分。知っているといっても、せいぜいドッジボールをやったり、スカートをめくったりした程度のことだったので、そういうのも悪くはありませんが、今となっては十分とは言えない。今ならもう少し別の話も出来るかも知れないですよね。
そして、先ほどのギャップや違和感もありつつ話をしていると、その奥の方から駆けっこが早かった○男くんの顔や、いつもおどけて笑わせてくれた○子ちゃんの顔が浮かび上がってきて、これは確かに知らないおじさんじゃない、ということにもなろうというもんです。その浮かび上がってくる顔が、自意識過剰のいやったらしい生意気盛りの大学生ではなくて、ほんとかうそか知りませんが、たぶん幻想ですが、純粋無垢な小学生の顔だ、というのはそんなに悪いことじゃないと思います。それはその頃の自分に出会うことでもあるのでしょうから。
いずれにしても、これからの日本は少子化であるだけではなくて、我々の世代も確実に減っていくわけですから、互いに励まし合って生きていく方がいい。
そのような意味でも、今回も有志の方が同窓会を企画し実現してくれたわけで、どうもありがとうございますと言いたいと思います。また、たまにお願いします。(2007年10月6日記)